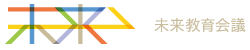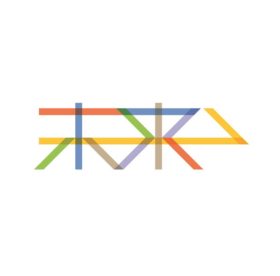- 未来教育リポート
- 2015.05.19
21世紀教育につながる日本らしさ| 一燈園・燈影学園 学園長 相 大二郎氏 (未来教育シンポジウム2015個別セッションリポート③)
教育ではなく「拝育」
世界中に「これが正しい教育である」と言い切れる教育はあり得ない。進学実績が良い学校が良い学校か、はたまた廊下がピカピカに輝いている学校が良い学校なのか?
創設者である西田天香さんは遺言を残した。「宣伝するな光っておれ!」。私立学校なのに宣伝するなというのは難しいこと。そのせいか、本校は日本で一番小さい私立学校だ。
天香さんの教育についての価値観は、一人一人の子供たちの光を拝んで育てる。教育ではなく拝育である。親や教師が一人一人の光を見出しているか?周りが光を感じ取っているか?光を拝んでいれば子供達は健全に成長していく。
子供達も大人たちも人間は皆全てよくあろうとしている。誰一人として悪人でいたいと思っている人はいない。泥水でさえ一晩コップに入れておけば泥は沈んでいく。人間の心もこれと一緒で、醜い泥の部分を持っていて、社会が混乱すると悪い部分が上に上がってきて、意地悪やいじめがでてくる。しかし、人間は自然と同じで、自然の摂理は意地悪やいじめは泥と一緒で沈んでいこうとしている。天香さんの言葉を借りれば、「水は常に澄もうとしている。大自然は常に人間の心をさまそうとしている」のである。
天香さんに「本校の教育を一言で表すと何でしょうか?」と尋ねた時、天香さんは「そうやなあ、自然に適う教育とでも言おうのかなあ」と答えた。自然に適う教育とは、自然の中で牛馬とともに農作業をするという意味ではない。自然といっても環境だけではない。環境は確かに子供たちに影響を与える。コンクリートよりも森や緑を見る方が落ち着く。森や緑には波動が流れていて、その波動を感じると脳からホルモンが分泌されるそうである。また自然は環境だけではない。山を覆う樹木が四季で彩りを変えて行ったり、何百年たてば朽ちていく。生老病死、諸行無常といった現象も自然そのものだ。3つめの自然とは自然の摂理。我々が男や女として生まれたこと。手足が2本づつ、指は10本づつ、目は前を向き、耳は横についていること。自分がこの容姿や能力に生まれたこと、その家に生まれたこと。それらはすべて自分で選んだことではない。大自然の摂理である。自然に適う教育というのは、3つめの自然の摂理に適うことを指しているかもしれない。

「教わる」教育と「伝わる」、「気づく」教育
大自然の摂理に従って授かった子供は心と体と脳を持って生まれてくる。自然に適うにはこの心と体と脳を鍛えなければならない。本校の教育の三本柱は、祈り、汗、学習。大自然から心を鍛えるのが祈り、体を鍛えるのが汗。脳を鍛えるのが学問。祈りは特定の宗教ではなく、感謝や反省、誓いといった人間としての祈りを意味している。汗はスポーツだけでなく、人の役に立つために自分や自分の時間、能力を捧げることを指す。今では奉仕やボランティアという言葉があるが、本校では80年間作務と呼んでいる。
子供が教わることができるのは、知識と技術。知識と技術は教わらないと身につかない。なぜなら答えがあるから。ただし命、心、自分、他人、家族、人生、自然といったものには特定の答えは存在しないから教えられない。一人一人が探求し、見つけるものである。世間では命は大事だと教えているが、教える必要はない。命の大切さを言葉で教えるという取り組みは原理的に難しいことだ。
本校では、お昼ご飯は小学生から高校生まで正座して黙っていただく。食事は話しながら食べた方が消化にもいいし、楽しいが、これは家庭でやってもらう。黙食であるから友人とは話をしないが、代わりに目の前のいわしやコメと話す。敏感な子は、自分がイワシを食べた時に、自分が命をいただいているということに気付く。
子供達は授業で金子みすゞさんの詩を学ぶ。
『大漁』
朝焼小焼だ
大漁だ
大羽鰮(いわし)の
大漁だ。
浜は祭りの
ようだけど
海のなかでは
何萬(まん)の
鰮のとむらい
するだろう。
この詩には金子みすゞさんの命の大切さに関する気づきが表現されているが、その詩を学び、暗唱しても、それぞれの児童が命の大切さに気づいたことにはならない。命は教えられない。気づかなければならない。
本校では毎朝瞑想を行う。これも「気づく」教育の一環である。
また多くのことは教えることはできず、「伝わる」のである。赤ちゃんが言葉を学ぶのは授業ではなく、親が「ご飯を食べましょうね」、「おむつを替えましょう」、「蝶々がきれいですね」と語りかけ続けることによって、ある日突然言葉を話し始める。まさに伝わるとしか言いようがない。同様に環境や生活習慣によってでしか伝わらないことが沢山ある。

情報技術(IT)と情報感性(IS:Information Sensitivity)
本校もIT教育は重視している。情報教室を作った時にある保護者が「うちの子供はパソコンを触らせたくない」と言ってきた。理由を尋ねると、そのお母さんはITの仕事に携わっていて、子供がマウスを持ってディスプレイを眺めていても子どもの心とディスプレイの絵と通いがないという。筆を持って書かれた絵には描き手の心が映るという。小さな子供の心にそういう経験をさせたくないという。そのお母さんには「これからの時代はITなしで生活するわけにはいきません。ITの弊害もあるがITを遮断するのではなく、IS教育もしっかりやるので認めてほしい」と言って納得してもらった。
Information Sensitivity、情報感性、とは環境としての自然、現象としての自然、摂理としての自然という3つの自然が発信する情報を受け取る力である。自然情報をキャッチする感性を養うための取組が、朝の瞑想や黙食である。
本校は正しい教育をしているわけではない。正しいとは何か、誰も判断できない。正しい教育といったとたん、他のやり方が間違った教育となり、争いが起こる。争いを起こさないように教育をしているのに、足元から争いの原因を作ってはいけない。だから、正しい教育と言うつもりはないが、教育にはぶれてはいけない軸足が必要である。その軸足は、自然に適うということだと創業者である天香さんは言う。

「なぜそろばんをやるのか?」
日常生活では算盤を小学校からやっているが、その理由は自然に適うから。人間は生まれながらに右脳と左脳を持っている。自然に適うには、左脳と右脳をバランスよく刺激する必要がある。左脳は論理、記憶、計算、分析をつかさどる。右脳はイメージ、感情、想像をつかさどる。そろばんは計算なので左脳を刺激している。5年生になると5ケタの計算の暗算ができるようになる。暗算になると子どもの脳は右脳に切り替わる。数字を見たら、算盤のデザインが浮かんでくる。
「なぜトイレを掃除するのか?」
よく「なぜ本校はトイレを掃除するのか?」と聞かれる。私どもは「なぜトイレを抜かすのですか?」と聞き返す。人間が生活する上で後始末は当然のことである。人間が後始末を怠った結果が環境破壊に繋がっている。これだけ環境がテーマになっているのに、最も身近な後始末を行わない理由がない。自分が汚したものを他人に始末してもらう小学校で育った結果、ポイ捨てをするというのは当然のことかもしれない。
「争いのない学内で12年間を過ごした子どもが社会に出て衝撃を受けないか?」
よく聞かれる質問。日本一小さな学校なので、1学年5人から10人である。60年で350人の卒業生しか輩出していない。学力で選抜するというよりも価値観選抜で、親や子ども自身が青春時代をここで過ごしたいと思う人が入ってくる。大学受験で成功したければ、進学校に行った方が良い。卒業生の中には、経営者、学者、芸術家(スイスローザンヌのバレーコンクールで振付をしている人もいる)がいる。震災直後、がれきの中で鎮魂のため行脚する僧侶がテレビや新聞に取り上げられたが、その僧侶は本校出身者。宗教家として歩む者もいる。哲学学会の会長をしている人もいる。はっきりしたものを持っているので、一目置かれる。変わっていることを不安がらず、軸足を立てることとで活躍する。
瞑想を通じて育まれているもの
「祈り」には感謝、反省、誓い、が含まれている。子ども達は元来、先生、友達、親、恵まれた環境への感謝と、自分はどこまで頑張ってやれているのかという反省という気持ちを持っている。だから自ずと頑張ろうという誓いが立つ。あの時はやらなかったから次は頑張ろうという、誓いを行っている。そのために朝の20分間の瞑想の時間がある。小学校一年生の子ども達も黙って座っている。「一体何を考えているのだろう」と思ったりもするが、そうした瞑想の中から素晴らしい詩が生まれている。以下は6年生の女の子の詩である。
『私と神様というひと』
どうして私はいるんだろう
どうして私は女なんだろう
どうして私は産まれてきたのだろう
全ての答えは神様が知っているんだ
きっと私は選ばれた者
何百ものいのちの種の中から選ばれた者
全てを決めたのは神様なんだ、きっと
でも神様はチャンスをくれただけなんだ
私に生きるチャンスをくれただけなんだ
きっとそうなんだ
神様っていう人は
すべての人にチャンスと希望をくれる人
それがきっと神様というひとなんだ
短い詩の中に「きっと」が4回も出てくる。これは、人から聞いたことではなく、間違っているかもしれないがきっとそうなのではないかとこの子自身が気づいたこと。瞑想の中で子供たちはこのようなことを考えているだろう。もう一つ小学6年生の詩を紹介したい。
『星』
星は人の数より多いと言うけれど
今私が見ている暗い空には何個星があるのだろう
きっといっぱいいっぱいあるのだろう
その中で輝いている星は何個だろう
人の人生も、いま輝いている人は何人だろう
この詩が京都新聞に掲載された翌日に一枚の葉書が学校に舞い込んて来た。「あなたの星と言う詩は5/29の京都新聞の全ての記事の中で最も強く私の心に響きましたと。私の70年の人生を思い起こしました。ありがとう。京都一市民」と書かれていた。
「本校に通うことができない子供たちに、家庭でどんなことをしたらいいのでしょうか?」
大切なのは「何をするか?」ではないか?想いが自然に形に現れる。形だけやってもダメで、熱意、愛情といった想いが重要。大切なことはお母さんやお父さんがお子さんのためにとそうやって一生懸命考えているというあり方がお子さんに伝わると思います。
本校では、子ども達が入ってきても、手を合わせなさい、挨拶をしなさい、履物をそろえなさいということは教えない。そういったことは知識や技術ではないから教えられない。周囲がやっていたら、自然にやる。子どもは両親がやることを真似する。
「家庭で大切している価値観が理由で学校において浮いてしまうということがあります。どうしたらいいでしょうか?」
ある小学校の先生から聞いたお話です。その先生の5年生のクラスには片耳が小さい生徒がいました。周りの生徒はその小さい片耳のことをからかうのですが、その生徒はいつも笑って平然としていて、それどころかいつもリーダーシップを発揮していた。先生は不思議に思い、ある日その生徒に「からかわれて辛くないの?」と聞くと、その生徒は初めて涙を流し自分の話を始めた。
自分は小さい頃から耳のことをからかわれていた。幼稚園の頃からかわれて泣いて家に帰り、母に「なぜ自分の耳は小さいのか?」と聞いた。お母さんは何も言わず、子どもの耳に口づけをして、お母さんはあなたの小さな耳が大好きよと言った。それから毎朝起きるたびに、耳に口づけをした。だから自分はいくらからかわれても悲しくないのですという。からかった子や、その子の親をたしなめるのもその母親が取りえた対応かもしれないが、自分の子どもがどんなことにも動じないでほしいという想いがあったのではないか。担任はその母親を尊敬したと言っていた。
【筆者所感】会場には20人ほどが車座になって、まるでたき火を囲むように穏やかに対話しました。静かな語り口で話す、哲学者のような居住まいの相先生に対して、参加者の質問は終わることがなく。予定の時間を大幅に延長しました。私も含め涙する参加者もいました。もともと相先生はていねいな「ですます調」でお話ししていましたが、字数の関係で「である調」で記載したことをお許しください。
未来教育シンポジウム2015関連記事
■未来教育会議とは | 時代が求める教育、日本の教育、そして社会と教育の関係 (未来教育会議シンポジウム2015リポート①)
■オランダ&デンマーク、未来の教育のヒントを探すスタディツアー|ダイジェスト・ムービー
■2030年の教育の未来シナリオ|画一的に学ぶ学校、地域とつながり学ぶ学校、社会と一緒に学ぶ学校
■「格差をなくす」 ―ドロップアウトを生まない教育の実現−|Learning For All 代表理事 李炯植氏からのプレゼンテーション (未来教育会議シンポジウム2015リポート②)
■「未来を創り出す」―サステナブルな社会の実現- |アショカジャパン創設者&代表理事・渡邊奈々氏からのプレゼンテーション (未来教育会議シンポジウム2015リポート④)
■すべての子どもたちに学習機会を| Learning For All 代表理事 李 炯植氏 / 事務局長 上野 聡太氏 (未来教育シンポジウム2015個別セッションリポート①)
- ライター
- 2018.11.27
- 12月13日 未来教育会議セミナー
人の可能性が最大限に開花する「人一生の育ちとは」
- 2018.11.26
- デンマークで人が一生学べる学校を立ち上げる日本人女性―ニールセン北村さん
- 2018.10.04
- 「人一生の育ち」を考える ’教育×経済’ 対話 第九回「教育格差を考える」
- 関連記事